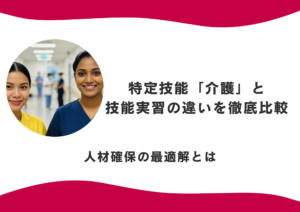
「外国人材を受け入れるなら、特定技能と技能実習のどちらを選ぶべきなのだろう…」「制度の違いがよく分からず、採用後にトラブルにならないか不安…」
そんなお悩みをお持ちの施設長・採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
まず大切なのは、ご自身の施設における「人材ニーズ」を正しく把握することです。
「今すぐ現場で働ける即戦力が必要なのか」「時間をかけて育成しながら将来の戦力を育てたいのか」によって、最適な制度は変わってきます。
即戦力を求めるなら<特定技能>
育成を重視するなら<技能実習>
を選ぶと良いでしょう。
この記事では、介護現場で外国人材を受け入れる際に知っておきたい特定技能と技能実習の違いを分かりやすく比較し、制度ごとのメリット・注意点を解説します。さらに、介護施設における外国人材活用の最適解や、受け入れ準備のポイントもご紹介します。
「結局、うちの施設にはどちらが合っているのか?」「外国人材に長く活躍してもらうためのポイントが知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能と技能実習の比較
外国人材を介護現場で受け入れる方法には「特定技能」と「技能実習」という2つの在留資格制度があります。どちらも外国人が日本で働ける仕組みです。ただし、目的や在留期間、労働条件、支援体制などの面で大きな違いがあります。
ここでは、介護施設が制度を選ぶ際に押さえておくべきポイントを、項目ごとに比較していきます。
目的の違い
介護分野で外国人材を採用する際、まず押さえておきたいのが「制度の目的」の違いです。
人手不足解消 vs 国際貢献
2つの制度は、そもそも成り立ちから方向性が異なります。
- 特定技能:介護分野をはじめとする国内の人手不足を解消するために創設された制度です。「労働者」を確保することが目的であり、即戦力となる人材を雇用するための仕組みです。
- 技能実習:日本の介護技術や知識を開発途上国へ移転し、母国の発展に貢献する人材を育成する「国際貢献」を目的としています。あくまで「実習」という位置づけであり、労働力の確保のために利用することは、本来の趣旨ではありません。
このように、制度の目的が異なります。外国人材の受け入れを検討する際には、理解しておきましょう。
介護施設のニーズに応じた活用
制度の特性を踏まえると、以下のような使い分けが考えられます。
-
- 即戦力を求める場合や、長期的に勤務できる人材を確保したい場合は、「特定技能」が適しています。
- 一方、時間はかかっても、施設の理念に基づき、一から人材を育て、国際貢献にも寄与したいという考えであれば、「技能実習」が選択肢となるでしょう。
以上の違いを理解しておくと、採用後のミスマッチを防ぎやすくなります。
在留資格と在留期間の違い
外国人材にどれくらいの期間、施設で活躍してもらえるのかは、非常に重要なポイントです。それぞれについて、詳しく解説していきます。
特定技能の在留資格と更新制度
特定技能「介護」の在留資格は「特定技能1号」に分類されます。在留期間は、通算で最長5年です。しかし、最大の特長は、在留期間中に国家資格である「介護福祉士」を取得すれば、在留資格「介護」へ移行できる点にあります。この「介護」ビザには在留期間の更新に上限がなく、永続的に日本で働き続けることが可能になります。
参考:厚生労働省「在留資格「特定技能1号」への移行について」令和7年版,2025.https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507781.pdf,(参照 2025-8-16)
技能実習ビザの制限
技能実習は、1号(1年目)、2号(2・3年目)、3号(4・5年目)と段階を経て、在留期間は最長5年です。期間満了後は原則帰国となり、継続して日本で働く場合は特定技能など別の資格への移行が必要です。
在留期間の比較
制度ごとの在留期間を表にまとめると次の通りです。
| 制度 | 在留期間 | 5年経過後のキャリアパス |
| 特定技能 | 通算上限5年 | 介護福祉士資格の取得により、在留資格「介護」へ移行可能(永続的な就労の道が開ける) |
| 技能実習 | 最長5年 | 原則として帰国 |
このように、在留期間の上限年数だけを見るとどちらも最長5年ですが、その後のキャリアパスが大きく異なる点は押さえておきましょう。特に介護施設にとっては、職員がどのくらいの期間働けるのかを見通しておくことは、人材計画に大きく影響します。
労働条件と転職の可否
雇用安定や人材定着を考える上で、労働条件と転職ルールを把握しておくことも重要です。
労働時間と時間外労働の規定
特定技能と技能実習のいずれの場合も、外国人に対して労働条件を引き下げることは許されません。労働基準法や最低賃金法など、日本国内の労働関連法規が適用され、日本人職員と同等以上の給与や待遇を確保する必要があります。
労働時間は、就業規則や労働契約で定められた範囲内で管理され、時間外労働や休日出勤を行う場合も、割増賃金の支払いを含めて適正な運用が求められます。
介護現場では慢性的な人手不足から時間外勤務が発生しやすいため、外国人職員にも無理のないシフト調整や休暇取得の確保が重要です。こうした労務管理の適正化は、定着率の向上にも影響するといえるでしょう。
特定技能外国人の転職可能性
特定技能の場合、同じ「介護分野」であれば在留資格を維持したまま他施設への転職が可能です。そのため、より良い労働条件や職場環境を求めて他の事業所へ移るケースも珍しくありません。採用した人材に長く働いてもらうためには、賃金や福利厚生の充実に加え、職場の人間関係や教育体制の整備など、総合的な魅力づくりが求められます。
一方、技能実習は、技能を習得することが前提のため、原則として転職は認められていません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、例外的に職場変更が許可されることもあります。
支援組織の役割
外国人が日本で安心して働くために、制度ごとに支援組織が設置されています。それぞれの役割について解説いたします。
登録支援機関の役割(特定技能)
特定技能で外国人を受け入れる場合、雇用主は「出入国管理及び難民認定法」に基づき、外国人が日本で円滑に生活・就労できるよう一定のサポートを行う義務があります。支援内容は多岐にわたるため、専門知識を持つ登録支援機関が委託を受けてサポートを行うのが一般的です。
主な支援内容は、以下のとおりです。
- 生活オリエンテーション:生活習慣・交通機関の利用・医療機関の受診方法など
- 日本語学習のサポート:教材提供や学習計画の提案
- 住居探しや契約の補助:不動産業者とのやりとりや契約立会い
- 各種手続きの支援:銀行口座開設・携帯電話契約など
- 相談窓口の設置:業務や生活の悩みに対応、必要に応じて通訳も手配
以上の支援は、外国人が安心して日本で生活・就労するために不可欠なものです。
監理団体の役割(技能実習)
技能実習において、受け入れ施設は、監理団体を通じて実習生を迎え入れるのが一般的です。監理団体は制度が適正に運用されているかを監督し、実習生と受け入れ施設の双方をサポートします。
監理団体の主な役割は、以下のとおりです。
- 実習計画の作成・提出:技能習得の計画策定
- 定期監査や訪問指導:労働環境・実習状況のチェック
- 生活・就労に関する相談対応:トラブル時の対応など
- 人権保護のチェック機能:長時間労働・賃金未払い・パワハラ等の防止
以上のように、監理団体は、実習生が本来の技能習得業務から外れてしまうことを防ぐために、多くの役割を担っています。
介護施設における外国人材活用の最適解
ここまで見てきたように「特定技能」と「技能実習」には目的や仕組みに大きな違いがあります。では、実際に介護施設が外国人材を受け入れる場合、どちらの制度を活用するのが最適なのでしょうか。
結論から言えば、多くの施設にとって「特定技能」の活用が有力な選択肢となります。ここでは、その理由となるメリットを整理してみましょう。
特定技能外国人の活用メリット
特定技能外国人を活用するメリットについて、3つを紹介します。
即戦力としての期待
特定技能の外国人は、在留資格を得るために「技能評価試験」と「日本語試験」の両方に合格していることが前提となります。そのため、ある程度の日本語でのコミュニケーション能力や、介護の基礎知識・技術を身につけてから現場に入ってくる人材です。
介護施設側にとっては、一から教育する負担が軽減され、現場に入ってすぐに戦力として働いてもらえる点が大きな魅力です。慢性的な人手不足を抱える介護現場では、この「即戦力性」が採用の決め手になるケースも多いでしょう。新人教育に割ける時間が限られている施設ほど、メリットを実感しやすいといえます。
長期的な人材確保の利点
技能実習は、原則として最長5年で帰国が必要です。一方、特定技能の場合は、条件を満たせば他施設への転職や、制度改正による将来的な長期在留の可能性も広がります。
特に「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留期間の上限がない在留資格「介護」へ移行できます。そうなれば、家族の帯同も可能になり、外国人職員が日本で腰を据えて長く働き続けることも可能になるのです。
利用者や家族との信頼関係構築
特定技能で来日する外国人材は、入国時点で一定の日本語能力を備えており、利用者様やご家族と日常的な会話を交わせるレベルにあります。
介護現場では単なるケア技術だけでなく「声かけ」や「傾聴」などのコミュニケーションが大きな比重を占めます。言葉を通じて関係を築ける点は、利用者の安心感や家族の信頼獲得につながります。
また、多文化的な背景を持つ職員が加わることで、施設全体の雰囲気がより柔軟で開かれたものになりやすく、利用者様にとっても「外国人と共に暮らす」という経験が新しい刺激となることがあります。
職員の多様性は、チーム力の強化にもつながります。結果的にケアの質が向上し、施設全体の雰囲気もよくなり、日本人を含めたスタッフの定着率向上も期待できるのです。
まとめ:施設長が考えるべきポイント

ここまで、特定技能と技能実習の違い、そして介護施設における活用の最適解について整理してきました。最後に、施設長が制度選択を行う際に意識しておきたいポイントをまとめます。
施設のニーズに応じた制度選択
まず大切なのは、ご自身の施設における「人材ニーズ」を正しく把握することです。
「今すぐ現場で働ける即戦力が必要なのか」「時間をかけて育成しながら将来の戦力を育てたいのか」によって、最適な制度は変わってきます。
- 即戦力を求めるなら特定技能
特定技能で来日する外国人材は、在留資格を得るために技能試験と日本語試験に合格していることが前提です。そのため、日本語での基本的なやりとりや介護の基礎知識を備えた状態で入職します。
現場に慣れるスピードも比較的早く、入浴介助や食事介助、夜勤対応など、人手不足が出やすい場面で即戦力として働ける点が魅力です。教育コストを抑えつつ、採用直後から戦力になってもらいたいと考えている施設に適しています。
- 育成を重視するなら技能実習
一方、技能実習は「技術移転」という目的が前提にあるため、受け入れ当初は介護の実務経験や日本語力が十分でない場合もあります。
施設側には、一から教育・指導することが求められます。しかし、その分、実習計画に基づいて体系的に教育できるメリットがあります。
長期的に自施設のやり方を身につけてもらえるので、育成環境が整っている施設や、指導体制に余裕がある施設にとっては有効な選択肢といえるでしょう。
いずれの制度を選ぶにしても、重要なのは、施設の現状と将来計画に合った制度を見極めることです。
例えば「すぐに人手不足を解消したいのか」「将来を見据えて安定的な人材を育てたいのか」「外国人材をどのポジションで活用したいのか」といった点を整理すれば、制度選択の方向性が見えてくるでしょう。
外国人材受け入れの準備と課題
制度を選んだ後、最も大切になるのが、「外国人材の受け入れ体制」です。単に採用するだけでは定着につながらないばかりか、早期離職やトラブルを招くリスクもあります。外国人材が安心して働ける環境を整えることこそ、人材活用のポイントなのです。
- 労働条件の整備
まず基本となるのは、日本人と同等以上の給与や勤務条件をきちんと確保することです。外国人であることを理由に処遇を下げることは法的に許されず、同じ業務を担う以上は平等な待遇が必要です。
さらに、時間外労働や休日取得についても、同様に管理しなければなりません。介護現場は人手不足であり、残業や休日出勤が増えやすい傾向があります。しかし、外国人材に過度な負担をかけると、不満や離職につながる可能性は高くなるでしょう。
労務管理を適正に行うことは、外国人材だけでなく日本人スタッフの働きやすさ向上にもつながります。
- 生活支援の準備
次に重要なのが、生活基盤を整えるためのサポートです。外国人材が来日した際にまず直面するのは、住居探しや交通機関の利用、医療機関の受診といった「日常生活の基盤を自力で整えることの困難さです」です。
たとえば、希望する住まいを確保できない、病院で言葉が通じないといった問題は、不安を高めるだけでなく、仕事へのモチベーションにも大きな影響を与えます。
だからこそ、事前に住居の確保や生活に必要なインフラを整えるサポートをすることで、外国人材が安心して暮らし、気持ちよく働ける環境につながります。生活面での安心感は、そのまま職場でのパフォーマンス向上にもつながるため、施設として積極的に支援していくことが望ましいでしょう。
- 教育・研修の実施
入職後の教育体制も重要です。特定技能人材であっても、実際の介護現場に慣れるには一定の時間を必要とします。
日本語学習の継続的なサポートや、施設のマニュアルに沿った研修を行うことで、より業務への理解を深めることが可能です。結果的に、定着率の向上も期待できます。
また、異文化への理解やコミュニケーションに関する研修を日本人職員と一緒に行えば、職場の一体感が生まれやすくなります。
- 既存職員との関係づくり
最後に、忘れてはならないのが「既存スタッフとの関係性」です。外国人材を受け入れると、職場の雰囲気や習慣が変わることもあるでしょう。
現場スタッフが、不安や誤解を抱かないように、事前に説明会を開いたり、外国人材と一緒に学ぶ研修を行ったりすることが大切です。
受け入れる側の意識が整えば、職場の一体感が高まり、外国人材も「ここで働き続けたい」と感じやすくなります。
以上のように、受け入れ体制をしっかり整えれば、外国人材は長く活躍し、施設にとって大きな力となってくれるでしょう。反対に、必要な準備を怠れば、せっかく採用しても早期離職やトラブルにつながる可能性があります。
つまり、受け入れ体制のあり方によって施設の雰囲気は大きく変わり、日本人職員を含めたスタッフ全体の定着にも影響を及ぼすのです。
介護専門の登録支援機関「アクタガワHRM」へご相談ください

特定技能外国人の受け入れで「資格取得のサポートがない」「定着率が伸び悩んでいる」等の課題を感じていませんか?
医療・介護専門のアクタガワHRMなら、グループ施設の運営ノウハウを活かした「入国時支援研修」に加え、「介護福祉士絶対合格プラン」への無料参加が可能です。
義務的支援の枠を超え、特定技能外国人のスキルアップと長期就労を強力にバックアップします。


特定技能外国人の採用を検討している方は、アクタガワHRMまでぜひお気軽にご相談ください。
関連記事・サイト紹介
静岡県内の特定技能介護人材の紹介と支援 | アクタガワHRM
静岡県限定の看護師求人・転職情報| ふじのくに静岡看護師求人ナビ
-
 登録者の声
登録者の声
【プレゼントキャンペーン】介護業界の人手不足と外国人労働者(特定技能)に関するアンケート
ふじのくに静岡介護求人ナビではサービスの質の向上を図るため、介護...
-
 特定技能採用お役立ちコラム
特定技能採用お役立ちコラム
【動画】特定技能外国人の働く様子と採用の流れをご紹介
特定技能とは 特定技能とは、国内で人手不足とされて...
-
 介護職関連資格
介護職関連資格
【2026年最新】処遇改善手当とは?あなたは貰える?介護職員処遇改善加算の全て
日本は現在「超高齢社会」を迎えています。20...
-
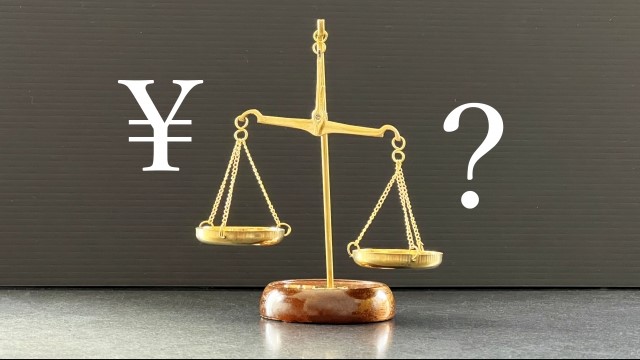 介護職の転職
介護職の転職
【2026年最新】介護職員・介護福祉士の夏のボーナス(賞与)が上がる職場をピックアップ
介護職員や介護福祉士として働くなら、給与面で待遇がよい職場を選び...





