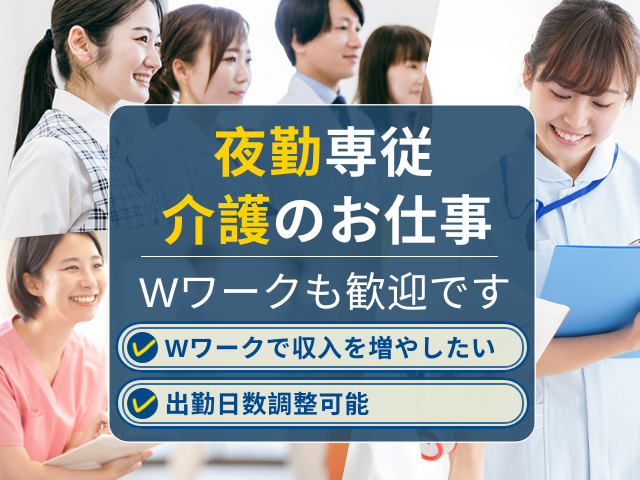「夜勤専従の介護スタッフ」として働くことは、健康管理に特に注意を払う必要がある職務です。夜勤による不規則な生活リズムや慢性的な疲労感が、身体的および精神的な健康に大きな影響を与えることが多く、適切な健康管理が不可欠です。
この記事では、夜勤専従でも身体を壊さないよう弊社の介護スタッフが実践する健康管理法について詳しく解説します。
健康管理の基本的な考え方や、実際に効果を上げている事例や統計データを交えながら、夜勤業務中や日常生活で実践できる実用的なヒントを提供します。
この記事を通じて、夜勤専従としての働き方を健康的に継続するための具体的な方法やアイデアを得ることができます。
Contents
介護職の夜勤の勤務時間について

介護職の夜勤の勤務時間は、「ロング夜勤」と「ショート夜勤」の2種類があります。
ショート夜勤は、介護施設によっては準夜勤と呼ぶこともあります。
ロング夜勤
1日を昼夜で2つに分けて配置する、2交代制の介護の夜勤をロング夜勤と言います。
勤務時間例として「夕方16時から翌朝9時まで」「夕方17時から翌朝10時まで」といった時間で勤務時間は16時間勤務するパターンが多いです。
ショート夜勤
1日を昼・夕方・夜の3つの時間に分けて配置する3交代制の介護の夜勤をショート夜勤と言います。「夜の22時から朝の7時まで」勤務時間は8時間勤務のパターンです。
出勤したらまずは、日勤のスタッフと情報交換するため引継ぎをします。
16時からの勤務であれば夕食や口腔ケアの介助があります。
21時からの勤務の場合は就寝介助があり、どちらも共通するのは夜間見回りです。
介護の夜勤といっても、ずっと起きて仕事をしているわけではありません。
朝5時までに1時間ほど休憩がとれるため、その間に仮眠をとることができます。
6時に利用者さんが起床となるため、体調確認・洗顔・着替えの介助があります。
続いて朝食の介助や服薬介助、口腔ケアをして、日勤のスタッフとの引継ぎをしたらその日の勤務は終了です。
夜勤専従は体を壊す?介護スタッフが直面する課題
労働時間が長い
介護職の夜勤では、1回につき16時間ほどの勤務時間となります。
どうしても長時間労働になってしまうため、体力がある人でなければ続きません。
夜間は日勤と比べると仕事の種類が少なく、力が必要になる仕事の回数は少ないのですが、その代わり長時間勤務になるデメリットがあります。
人員が少なく緊急時の対応に不安がある
介護職の夜勤はどの介護施設でも、職員配置を少なくしています。
施設によっては1人で介護しなければならない場合もあるでしょう。
このような状況では、1人の介護職員に大きな責任がかかることになります。
夜間は利用者さんが急変することもあるため、その際には1人で対応しなければなりません。
夜勤専従では、介護職としての経験が求められるでしょう。
どのような状況でも自分で考えて、臨機応変に対応できる力が求められます。
しかし、介護職の経験がある方でも、緊急時に不安を感じる場合は少なくありません。
介護職は人の命を預かる立場で責任が重くのしかかるため、その重圧に耐えることができなければ、夜勤専従だときついと感じるでしょう。
睡眠不足で疲れがたまりやすい
夜勤専従の介護職員にとって、睡眠不足は深刻な問題です。夜勤という不規則な勤務形態は、自然な睡眠リズムを乱し、十分な休息を確保することを難しくします。これにより、身体的および精神的な健康への悪影響が懸念されます。
また、介護職の夜勤は人員が少なく、1人で身体介護にあたることも多いため、力仕事はあります。
日勤なら体力的に無理なら別のスタッフに頼むことができますが、夜勤だと自分が対応しなければならない状況が少なくない点にも注意してください。
変則勤務なので体調を崩しやすい
夜勤専従の介護職員にとって、生活リズムの乱れは避け難い課題の一つです。夜勤により通常の昼間の生活パターンが逆転することで、身体的および精神的な健康に様々な影響を及ぼします。
まず、身体的健康への影響として、体内時計が乱れることで睡眠の質が低下し、慢性的な疲労感や免疫力の低下を招く可能性があります。例えば、夜勤明けに十分な休息を取れない場合、翌日の業務に支障をきたすだけでなく、長期的には心血管疾患や代謝異常のリスクが高まることが研究で示されています。
夜勤専従スタッフが身体を壊さないための心構え
夜勤専従は体調管理が第一の職務ではありますが、夜勤スタッフとして働く大きなメリットもあります。
夜勤専従で働くメリット
○高収入を得やすい
日勤と比べて夜勤は高収入になるというメリットがあります。
夜勤は「深夜割増賃金」「夜間手当」がつくため高収入が可能です。
深夜割増賃金は法律で決められており、深夜労働者には必ず支払われます。
対象となる勤務時間は、22時~翌朝5時までで、時給の25%が上乗せされます。
また、「夜間手当」は法律で決められているわけではありませんが、施設によって独自に夜間手当を支払うところがあります。
介護施設の種類によっても異なりますが、1回あたり夜間手当を4,000円以上支給する施設が多いため、夜勤は高収入になりやすいでしょう。
もちろん、1日8時間を超える法定労働時間に対しては、25%以上の割増賃金もつきます。
夜勤専従は長時間労働となることが多いため、割増賃金はつくと考えておきましょう。
○休日が多い
介護職の夜勤は休日が多くなるのも魅力のひとつです。
1回の労働時間は長くなりますが、勤務の翌日は休みとなり、その翌日は公休日とする施設が多くなっています。
夜勤専従なら出勤日数が少なくなり、プライベートの時間を確保しやすいでしょう。
人によって希望の働き方は異なりますが、1回の勤務時間が短く毎日出勤するより、1回の勤務時間が長く多くの休みを得たいなら、夜勤専従がおすすめです。
休みの回数が多い夜勤専従なら、休みの日に趣味を楽しんだり、家族との時間を過ごしたりしやすくなります。
空いた時間で習い事や勉強をしたい方や、休日にゆっくり過ごしたい方にとっては、夜勤専従の働き方が向いているでしょう。
○日勤と比べて忙しくない
介護職の夜勤は日勤に比べると業務量が少ない傾向にあります。
夜間は少ない人員で緊急対応を行う責任や大変さはありますが、反対に緊急の事態が無い場合は見回りの時間が多く、利用者様への対応は多くはありません。
夜勤業務の乗り越え方
生活リズムが変則的になる介護職の夜勤は、身体の負担を減らす為に日ごろから自身を労わることが重要です。
夜勤中は体に負担の少ない食事をとり、夜勤明けは軽く睡眠をとったあとは普通に過ごすと、不規則な生活リズムを整えやすくなります。
○夜勤明けは早めに寝る
夜通し勤務する介護職の夜勤は、勤務後は眠気を感じます。
そんな時は無理をせず2~3時間の仮眠をとりましょう。
朝長時間睡眠をとってしまうと夜眠れなくなることもありますので、短めの睡眠をとり、その日の夜は早めに就寝を心がけますと、疲労軽減が期待できます。
○夜勤明けの日中はリフレッシュに充てる
夜勤明けに仮眠をとった後は、なるべく普段通り過ごしましょう。規則正しく夜に就寝出来るよう、日中は外出や趣味・用事を済ませる等活動的に過ごすことがオススメです。
○勤務中の食事に気を付ける
介護職の夜勤中は消化の良い食事を心がけ身体の負担を軽減しましょう。
身体が軽く過ごせると、介護職の夜勤勤務中のきつさを軽減することが期待できます。規則的な食事をとることで、体内時計を保つことが可能です。
夜勤中の食事はできるだけ軽いものを、日中はしっかりと食事を取るよう心がけましょう。
夜勤専従スタッフが実践する健康管理法10選
夜勤専従者が安定した生活リズムを確立するためには、具体的なステップや日常的な習慣の見直しが不可欠です。
本セクションでは、規則的な食事時間や休息時間の設定、週末のリズム調整など、実践的なアドバイスを通じて、日中の活動と夜勤のバランスを効果的に取る方法をご紹介します。
夜勤前の準備と心構え
夜勤に入る前の準備と心構えは、健康を維持し快適な勤務を行うために非常に重要です。適切な準備を行うことで、身体的・精神的な負担を軽減し、夜勤中のパフォーマンス向上につながります。
まず、適切な食事と水分補給が不可欠です。夜勤前には消化の良い軽食を摂取し、十分な水分を補給することでエネルギーを維持し、集中力を高めることができます。特に、タンパク質や複合炭水化物を含む食事を心掛けると良いでしょう。
次に、ストレッチや軽い運動を取り入れることが推奨されます。身体を軽く動かすことで血行が促進され、筋肉の緊張をほぐすことができます。また、短時間のウォーキングやヨガなども効果的です。
さらに、ポジティブな思考法を実践することも重要です。夜勤に対する不安やストレスを軽減するために、リラクゼーションテクニックや深呼吸法を取り入れ、自分自身をリフレッシュする時間を確保しましょう。
最後に、十分な睡眠と休息を確保することも忘れてはなりません。夜勤前にはリラックスできる環境を整え、質の高い睡眠を取ることで、翌日の勤務に備えることができます。
これらの準備と心構えを実践することで、夜勤専従者は健康を維持し、より快適に仕事を続けることが可能になります。自分に合った方法を見つけ、継続的に取り入れることが大切です。
夜勤明けのスムーズな休息方法
夜勤明けの疲労回復を促進し、次の勤務に向けてリフレッシュするためには、効果的な休息方法が欠かせません。
まず、短時間の昼寝を取り入れることで、体力の回復を助け、集中力を高めることが可能です。昼寝は20~30分程度が理想とされており、深い眠りに入らずにすっきりと目覚めることができます。
さらに、リラクゼーションテクニックを実践することで、精神的なストレスを軽減し、心身のバランスを整えることができます。深呼吸や瞑想、軽いストレッチなどを取り入れることで、リラックス効果が高まり、翌日の準備が整います。また、適切な食事や水分補給も重要です。栄養バランスの取れた食事を摂ることで、体内のエネルギーを補充し、疲労回復をサポートします。水分をしっかりと摂ることで、体内の水分バランスを保ち、体調を整えることができます。
これらの休息方法を組み合わせて実践することで、夜勤明けの疲労を効果的に解消し、次の勤務に向けて充実した状態を維持することができます。自分に合った方法を見つけ、継続的に取り入れることで、健康的な夜勤ライフを送るための基盤を築きましょう。
睡眠の質を向上させる
夜勤専従者にとって、質の高い睡眠は心身の健康を維持し、日々の業務を効率的にこなすために不可欠です。適切な睡眠は疲労回復やストレス軽減、集中力の向上に直結し、介護現場でのパフォーマンスにも大きな影響を与えます。
質の高い睡眠を得るためには、寝室環境の整備や適切な寝具の選択、睡眠前のリラックス習慣の確立、カフェインの摂取管理など、様々な側面からのアプローチが必要です。これらの方法を実践することで、夜勤専従者が健康を維持しながら、持続可能な働き方を実現することが可能となります。
快適な睡眠環境を整える
快適な睡眠環境を整えることは、質の高い睡眠を確保するために非常に重要です。まず、寝室の温度を適切に保つことが必要です。快適な睡眠を促進するためには、室温を約18℃から22℃に設定することが推奨されます。この温度範囲は、体温が下がりやすくなり、深い眠りに入りやすくします。
次に、照明の調整も重要です。寝室はできるだけ暗くし、自然光を遮るために遮光カーテンを使用することで、外部からの光を遮断します。夜勤明け後の寝室では、明るすぎる照明は体内リズムを乱す原因となるため、間接照明や暖色系のライトを活用しましょう。
また、騒音対策も欠かせません。睡眠中に外部の音が気になる場合は、ホワイトノイズマシンや耳栓を使用することで音を効果的に遮断し、静かな環境を保つことができます。
寝具選びも快適な睡眠環境を作るための重要な要素です。自分に合ったマットレスや枕を選び、体圧分散性に優れたものを使用することで、体の負担を減らし、リラックスして眠ることができます。また、季節に適した寝具を選ぶことも、快適な睡眠をサポートします。
最後に、快適な睡眠環境を維持するためには、日常的な工夫や習慣も大切です。例えば、寝室を清潔に保ち、整理整頓された状態を維持することや、就寝前のルーティンを決めることで、体と心をリラックスさせ、自然に睡眠モードに入ることができます。これらのポイントを実践することで、夜勤専従であっても質の高い睡眠を確保し、健康を維持することが可能となります。
睡眠サイクルを守る
睡眠サイクルを守ることは、夜勤専従の介護職員にとって極めて重要です。人間の生体リズムは、身体の各機能が適切に働くために必要なリズムパターンを持っており、これが乱れると健康に深刻な影響を及ぼします。特に、夜勤を担当することで昼夜の生活パターンが逆転しやすく、睡眠サイクルの維持が難しくなります。睡眠不足や質の低下は、免疫力の低下、集中力の欠如、さらにはメンタルヘルスの問題に繋がる恐れがあります。
夜勤専従者が健全な睡眠サイクルを維持するためには、まず、規則的な就寝・起床時間を設定することが基本です。毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計が安定し、質の高い睡眠を確保しやすくなります。また、シフトの調整方法として、徐々にシフトを変更することで急激なリズムの乱れを防ぐことが推奨されます。例えば、シフト交代の際には1週間単位で少しずつ時間をずらすなど、身体が適応しやすいペースで調整を行いましょう。
睡眠不足を補う方法
夜勤によって生じる睡眠不足を効果的に補うためには、いくつかの具体的な戦略やテクニックを実践することが重要です。これらの方法を取り入れることで、質の高い休息を確保し、日中のパフォーマンスを向上させることが可能になります。
以下に、簡単に実践できる方法をいくつかご紹介します。
短時間の仮眠を取る: 15~20分程度のパワーナップは、集中力や気分をリフレッシュさせるのに効果的です。適切なタイミングで仮眠を取ることで、夜勤中や勤務後の疲労感を軽減できます。
栄養補助食品の活用: メラトニンやビタミンB群など、睡眠の質を向上させるサプリメントを取り入れることで、身体のリズムを整える助けになります。ただし、使用前には専門家に相談することをおすすめします。
リラクゼーションエクササイズ: 深呼吸やストレッチ、ヨガなどのリラクゼーションエクササイズは、心身の緊張をほぐし、スムーズな入眠を促進します。夜勤前や勤務後に取り入れることで、リラックスした状態で休息を取ることができます。
睡眠補助アプリの利用: 瞑想ガイドやホワイトノイズ、リラクゼーションミュージックなどを提供する睡眠補助アプリを利用することで、環境を整え、質の高い睡眠をサポートします。スマートフォンやタブレットで手軽に設定できるため、夜勤専従者にとって便利なツールです。
これらの方法を組み合わせて実践することで、睡眠不足を効果的に補い、健康を維持しながら夜勤を続けることが可能になります。自分に合った方法を見つけ、継続的に取り入れることが鍵となります。
夜勤中の適切な食事タイミング
夜勤中の適切な食事タイミングは、エネルギーを維持し、集中力を保つために非常に重要です。夜勤の間にバランスの取れた食事スケジュールを組むことで、長時間の勤務を健康的に乗り切ることができます。
まず、夜勤の開始前にはしっかりとした夕食を摂ることが推奨されます。夕食にはタンパク質や複合炭水化物を含むバランスの良い食事を心がけることで、持続的なエネルギー供給が可能になります。例えば、鶏肉や魚、全粒穀物、野菜を中心としたメニューがおすすめです。
勤務中に摂取する軽食のタイミングも重要です。夜勤の最初の休憩時間には、軽食としてフルーツ、ナッツ、ヨーグルトなどを選びましょう。これにより、血糖値が安定し、午後からの業務に備えることができます。
さらに、夜勤の中盤にはメインの食事を摂ることが効果的です。この時間帯には、消化に良くて栄養価の高い食事を選ぶことがポイントです。例えば、野菜たっぷりのサラダやスープ、バランスの取れたサンドイッチなどが適しています。
カフェインや糖分の摂取管理も欠かせません。カフェインは一時的に集中力を高める効果がありますが、摂りすぎると後半の業務で眠気を感じやすくなります。適度なカフェイン摂取を心がけ、午後遅く以降は控えるようにしましょう。
糖分の摂取についても注意が必要です。糖分は短期的なエネルギー供給には効果的ですが、急激な血糖値の上昇と下降を招くため、低GI食品を選ぶことがおすすめです。例えば、全粒粉のクラッカーやナッツ、ダークチョコレートなどが良い選択です。
■夜勤専従スタッフの勤務前後の食事例
勤務開始前(夕食): 鶏肉のグリル、玄米、野菜の蒸し物
最初の休憩時(軽食): バナナ、アーモンド、ヨーグルト
中盤の休憩時(メインの食事): 野菜たっぷりのサラダ、全粒粉のサンドイッチ、スープ
勤務終了前(軽食): ダークチョコレート、ナッツ、フルーツ
また、夜勤中は水分補給も忘れずに行いましょう。水やハーブティー、低カフェインの飲み物を定期的に摂取することで、脱水を防ぎ、身体の調子を整えることができます。
最後に、食事の質とタイミングを意識することで、夜勤中のエネルギー維持と集中力の向上が期待できます。規則正しい食事スケジュールを守り、バランスの取れた食事を心がけることで、健康を保ちながら効率的に夜勤をこなすことが可能です。
運動とストレッチの実践
夜勤専従の介護職員が健康を維持するためには、適度な運動とストレッチが欠かせません。これらの活動は身体の柔軟性を高め、疲労を軽減するだけでなく、精神的なリフレッシュにも効果的です。
○肩回しストレッチ
デスクワークや立ち仕事の合間に取り入れやすい肩回しストレッチです。肩をゆっくりと前回し、次に後ろ回しを行います。各方向で10回ずつ繰り返し、肩周りの緊張を和らげましょう。
○首の側屈ストレッチ
立った状態または椅子に座った状態で、頭をゆっくりと右側に倒し、左手で頭を優しく押さえます。反対側も同様に行い、首の側面の筋肉を伸ばします。各側で15秒間キープしましょう。
○腕の伸展ストレッチ
両腕を前に伸ばし、手を交差させて指先を組みます。肩の高さまで持ち上げ、腕をまっすぐ前方に伸ばします。この状態で20秒間キープし、背中や肩の筋肉を伸ばします。
○背中のストレッチ
椅子に座った状態で背筋を伸ばし、両手を前に伸ばします。息を吐きながら上体を前に倒し、背中全体を伸ばします。深呼吸をしながら30秒間キープします。
○足首の回旋ストレッチ
立った状態で片足を前に出し、もう一方の足を後ろに引きます。足首をゆっくりと回転させ、関節の柔軟性を高めます。各方向で10回ずつ行いましょう。
これらのストレッチは、短時間で簡単に実践できるため、夜勤の合間や勤務前後のリラックスタイムに最適です。定期的に取り入れることで、筋肉の緊張を緩和し、血行を促進する効果が期待でき、結果として疲労の蓄積を防ぎ、健康的な夜勤生活をサポートします。
介護職員に適した筋力トレーニングの実践
介護職員に適した運動習慣を確立することは、日々の業務で求められる身体的負担や動作に対応するために非常に重要です。特に、長時間の立ち仕事や重い物の持ち運びなど、身体に大きな負担がかかる作業が多いため、適切な筋力トレーニングや有酸素運動を取り入れることが求められます。
まず、筋力トレーニングは、筋肉の強化と持久力の向上に役立ちます。以下は、介護職員に推奨される具体的な運動プログラムです。
スクワット: 腿と腰の筋力を強化するために、週に3回、各セット10回を目指します。
プッシュアップ: 上半身の筋力を鍛えるために、週に2回、各セット8回を実施します。
バックエクステンション: 背筋を強化し、姿勢を改善するために、週に3回、各セット12回を行います。
次に、有酸素運動は、心肺機能の向上と持久力の増加に効果的です。以下の有酸素運動を日常的に取り入れることをお勧めします。
ウォーキング: 1日30分、週に5回行うことで、心肺機能を高めます。
ジョギング: 週に2回、各セッション20分を目指して行います。
サイクリング: 週末に1回、屋外でのサイクリングを楽しみながら有酸素運動を行います。
ストレス管理とメンタルケア
夜勤中のストレスを軽減するためには、夜勤特有の業務環境や人間関係から生じるストレス要因を正確に把握し、効果的に対策を講じることが重要です。以下に、具体的なストレス軽減方法を紹介します。
定期的な休憩の取り方: 夜勤中に適切なタイミングで休憩を取ることで、心身のリフレッシュを図ります。短時間の休憩を計画的に挟むことで、疲労の蓄積を防ぎ、集中力を維持することができます。
コミュニケーションの改善: 同僚や上司との円滑なコミュニケーションを図ることで、職場のストレスを軽減します。オープンな対話を促進し、問題や課題を共有することで、協力して解決策を見つける環境を整えます。
ストレス発散のための趣味の取り入れ方: 仕事外の時間に趣味を持つことで、ストレスを効果的に発散できます。例えば、読書や音楽鑑賞、軽い運動など、自分に合ったリラクゼーション方法を取り入れることが推奨されます。
さらに、リラクゼーションテクニックやマインドフルネスを実践することで、心の平穏を保つことも効果的です。夜勤中のストレス管理は、継続的な努力と自己ケアが求められますが、これらの方法を取り入れることで、健康的な夜勤ライフを送ることが可能になります。
夜勤専従の求人を探すポイント
○夜勤中の休憩室や仮眠室の有無を確認
介護職の夜勤で働く際、休憩時間は仮眠をとるスタッフも多いです。
施設によっては休憩室や仮眠室があり、ゆっくり休める環境を整えている職場もあるので、
休憩がしっかりとれる環境課そうかを確認することが大切です。
○夜勤中の休憩時間の確認
職場がきちんと休憩時間を確保しているかも確認することが重要です。
実際に介護サービス利用者様の状況によって休憩が取れなかったなんてこともあります。
職場を選ぶ際は、休憩が取れないのは当たり前という職場環境になっていないかは注意が必要です。
休憩がしっかりとれないと心身の負担が大きく介護職の夜勤がきつく感じる要因となるでしょう。
○夜勤の回数を確認
介護職の夜勤に回数の制限はなく、職場によって一人当たりの夜勤の回数にばらつきがあります。
介護職の夜勤がきついと感じるかは月にどれくらい夜勤シフトに入っているかも関わってきます。
夜勤シフトは人員確保に苦労している介護施設も多いので、夜勤の回数がどれくらい求められているかも確認が必要でしょう。
○夜勤手当の確認
夜勤そのものは法律で深夜割増金を支給することが決まっている為、日勤と比較して高収入が期待できます。勤務先に夜勤手当があるかは勤め先の施設によって異なりますので、どの様な手当てがあるのか就労前に事前に確認するのがオススメです。
介護職の夜勤はこんな人におすすめ

介護職の夜勤はきついイメージがあり人を選びますが、次に該当する方にはおすすめの働き方です。
- 収入を上げたい
- 休日を多くしたい
- あまり忙しくない方が良い
- 十分な体力がある
- 少人数でも対応できる経験やスキルがある
- 日勤と合わせてダブルワークをしたい
これまで介護職の経験があり、十分な体力がある方に夜勤専従が向いています。
さらなるスキルアップのために学校に通いたい方や、プライベートを充実させたい方、ダブルワークをして稼ぎたい方にも向いているでしょう。
まとめ
この記事では、夜勤専従スタッフが実践する健康法についてお伝えしました。
収入アップや休日を増やす意味で夜勤専従を希望される方は、紹介した情報を参考にしながら、自分に合った働き方なのかもう一度見直してみましょう。
そのうえで夜勤専従での働き方をしたいと考えるなら、ご自身が働く施設への相談や、転職を進めるのが良いでしょう。
特に施設の情報収集は重要なため、まずはキャリアコーディネーターに相談してみてはいかがでしょうか。
効率的に稼ぎたい、日中に時間を取りたい、副業として夜勤で働きたいなど、様々な理由で夜勤専従で働くスタッフは増えています。
ぜひ、自分に合った働き方を検討してみてください。

【関連サイト紹介】
-
 最新ニュース介護職の転職
最新ニュース介護職の転職
【2025年最新情報】介護職の処遇改善手当とは?もらえる条件やその支給額について
介護職は、身体や認知機能に障害を持つ人々の日常生...
-
 介護職の転職
介護職の転職
【介護職のお悩み】介護職に向いていないのかも辞めたい
介護職では人手不足が常態化し、そのプレッシャーから「辞めたい」と...
-
 介護職の転職
介護職の転職
介護士が介護業界での転職に失敗しないため~5つのポイントを解説
介護職の転職失敗事例を踏まえて、介護士が転職で失敗しないためのポ...
-
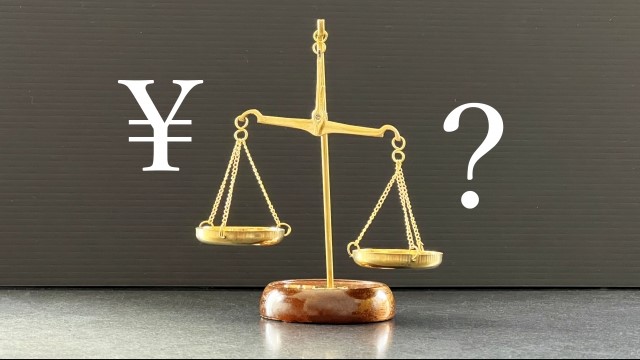 介護職の転職
介護職の転職
【2025年6月最新】介護職員・介護福祉士の夏のボーナス(賞与)が上がる職場をピックアップ
介護職員や介護福祉士として働くなら、給与面で待遇がよい職場を選び...